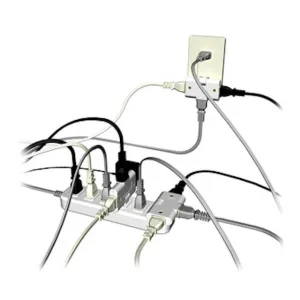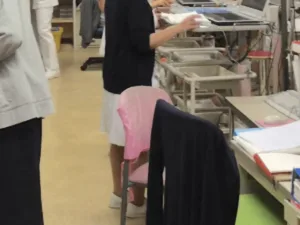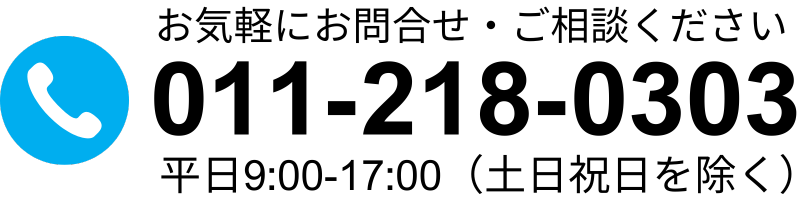
入院経験から学んだ、病棟廊下の「手すり」と「消火栓」設置のポイント

こんにちは、代表の澤です。
私事ですが、私は以前に椎間板ヘルニアの手術のため、整形外科に3週間ほど入院していたこことがあります。
術後2日目でなんとか歩くことを許され、最初に私がしたことは、病室のベッドから病棟の中央にあったトイレに行くことでした。
身体にメスを入れたのはその時が最初でしたが、「手術の後に普通に歩くことが、こんなにも大変なのか…」と、初めて患者さんの立場にたって、実感することができました。
また、自分のベッドからトイレ行き着くまでの間、廊下の壁に手すりがあることの有難さを実感しました。
そこで今回は、私自身の入院患者としての経験と病院設計の視点から、「廊下の手すり」と、火災時に使用する「消火栓」の設置のポイントについて、お話ししたいと思います。
設計の細かな工夫が、患者の安心感や回復のスピード、使いやすい病院環境を左右します。ぜひ最後までお読みください。
目次
患者に優しい手すりの形状とは?
入院中、手すりを使いながら廊下を歩く患者さんをよく観察していました。すると、多くの人が手すりをしっかり握るのではなく、体重を移しながら移動していることに気づきました。
術後の私もそうでしたが、患者さんは様態によって握力も弱くなっており、自分の足腰に負担が掛からないように、杖をつくような感じで、手すりの上で手を滑らせながら目的地まで移動しています。
そのため、手すりの断面形状は、円形より楕円形の方が、体重をあずけやすく使いやすいと考えられます。実際、10年ほど前から各メーカーが楕円形の手すりを開発・販売しています。
こうした細かな配慮が、患者さんにとって移動のしやすさと安心感につながります。
手すりを切らない消火栓の工夫
もう一つ、患者さんにとって廊下の手すりは、途切れなく続いている方が安全で使いやすいものです。
しかし、病院の廊下に壁に埋め込まれた消火栓があり、長さにして60cmほどですが、廊下の壁の手すりが途切れているのをよく見かけます。
一般的な建物内部の消火栓の高さは約90cm。
一方、手すりの高さは70〜80cmのため、扉と干渉してしまうことから、火災時の安全性を優先して、その部分だけ手すりを取りやめるケースが見られます。
近年はこの問題を解決するため、手すりスペースを確保した消火栓や、高さ60cmほどのロータイプ型消火栓も登場しています。これらを採用すれば、手すりを途切れさせることなく設置可能です。
業者さんのアドバイスを受けながら、最適な設計を検討すると良いでしょう。
ちなみに、消火栓は消防隊が使用するものと思われがちですが、本来は初期消火のために設置されており、誰でも使えるよう操作しやすく設計されています。
防火訓練の際には、一度開けてみて、使い方をスタッフ全員で確認しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、私自身の入院経験から学んだ、病棟廊下の「手すり」と「消火栓」設置のポイントについて解説しました。
入院患者の視点に立つと、普段は意識しない小さな設計の工夫が、大きな安心につながることがわかります。手すりの形状や消火栓の配置といった細かい部分にもこだわり、安全で快適な病院環境を整えていくことが大切です。
病院建築でのお困りごとは、SAWAにお気軽にご相談ください。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください
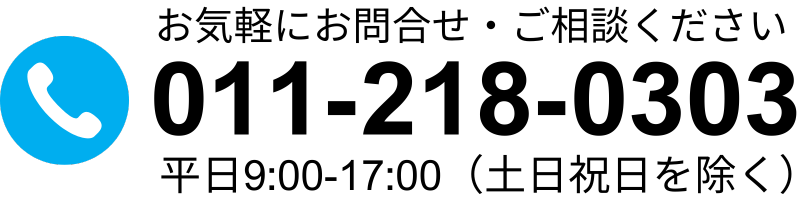
![[病院専門の設計事務所] SAWA医療設計株式会社](https://sawa30.com/wp-content/uploads/2025/01/sawa_logo1.png)